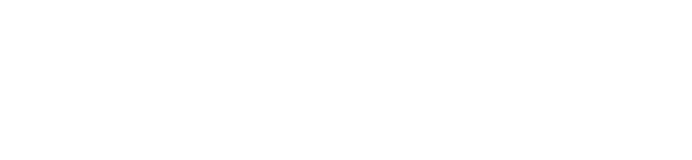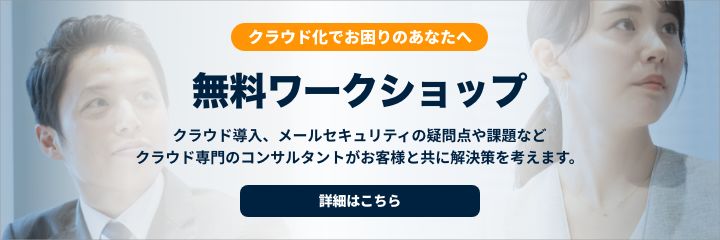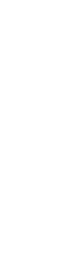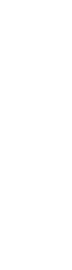過去のメールを残すべき?削除すべき?データ管理の最適解
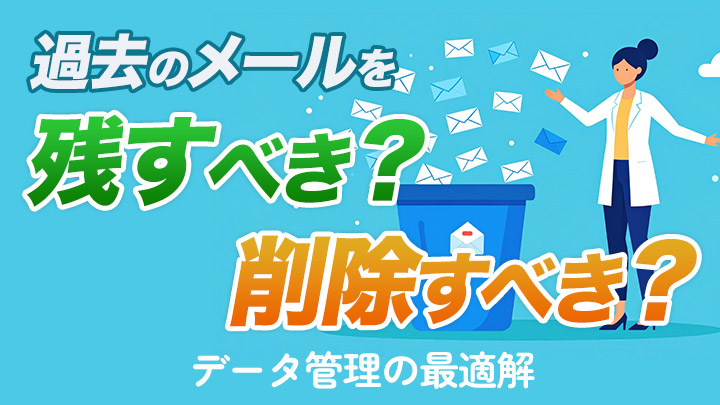
企業活動において「メール」は業務連絡・契約交渉・社内通達など、あらゆる情報のやり取りを担う重要なツールです。メールの記録は、証拠やコミュニケーションの参考として役立つ一方、過去のメールの保存が続けば続くほど、情報漏洩やセキュリティインシデント、ストレージの圧迫、個人情報保護などの課題が浮上します。
こうした背景のもと、メールのセキュリティを担当する企業のIT担当の方や、毎日多くのメールをやり取りする総務や営業部門の方などは、「メールをどこまで保存するべきか?」「何を削除してよいか?」という判断に日々頭を悩ませているのではないでしょうか。
本記事では、メール保存と削除それぞれのメリット・リスクを整理し、業務と法令遵守の両立が可能なメール管理の考え方と対策を紹介します。貴社のメール運用ポリシーの見直しに、ぜひご活用ください。
クラウドサービス導入のご相談は
無料ワークショップでご相談を
メールを保存するメリット
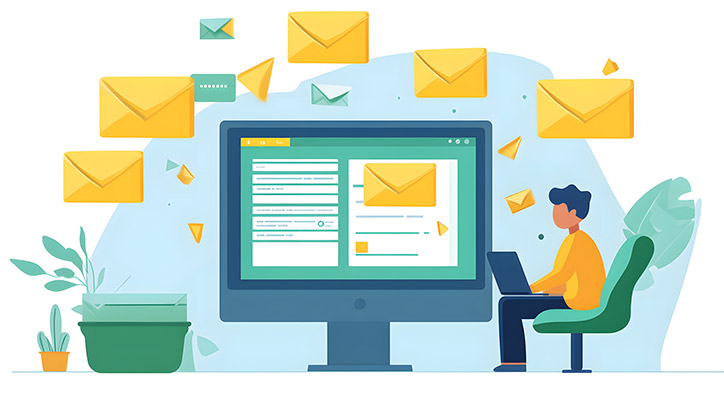
日々の業務でやり取りされるメールには、契約内容や業務指示、顧客対応の履歴など、企業活動の根幹に関わる情報が多く含まれています。こうしたメールを適切に保存することで、トラブル時の証拠として活用できるだけでなく、社内ナレッジの蓄積や監査対応にも有効です。
まずは、企業におけるメール保存の主なメリットを整理し、部門ごとにどのような効果が期待できるのかを具体的に見ていきましょう。
証拠保全(取引履歴・契約内容の証明)
日々のメールには、商談内容や契約条件、業務指示などの重要なやり取りが含まれます。こうした記録は、万が一のトラブル発生時に「言った・言わない」を防ぐ証拠として活用できます。
特にIT担当者は、監査対応や法的な証明資料の保全として、適切なメールの保存体制の整備が求められます。
チームで対応ができる
トラブルや問い合わせ対応が発生した際、適切に保存・管理されたメールがあれば、関係者間で情報を即座に共有でき、チームでの迅速な対応が可能になります。
とくに、メールのやりとりが多い部署では、過去のメールが業務マニュアルやナレッジとして機能することもあり、過去メールを活用することで業務品質の安定にもつながります。
また、検索性の高い保存体制が整っていれば、過去の対応履歴を活用して属人化の防止や、スムーズな業務の引き継ぎが実現できることがメリットです。
監査・コンプライアンス対応
外部監査や内部統制の観点からも、過去メールの記録は重要です。情報漏洩や不正の有無を確認する際、記録が残っているかどうかが調査の成否を分けることもあります。
そのため、メールの保存体制の整備は、社内全体のセキュリティ対策の一環として、日頃から取り組むべき要素です。
メールの保存に関するルールを制定や、長期保存ができるストレージの用意は欠かせません。
メールを削除するメリット
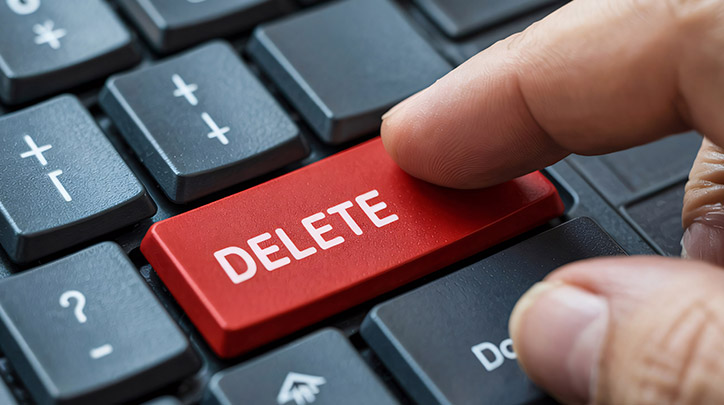
- 業務効率の向上
- ストレージコストの削減
- セキュリティ体制の強化
重要なメールや取引のやり取りのメールは保存しなければなりませんが、迷惑メールなど「明らかに不要なメール」を削除しましょう。
特に、迷惑メールや業務に無関係なメールを蓄積させることで、セキュリティリスクや保管コストの増加を招く恐れがあります。
しかし、一つ一つのメールを精査すると、業務が滞りますので、システムを利用したメール削除の実現がおすすめです。
いつもメールボックスが整理されていれば、メールの見落としも少なくなります。
メール保存・削除の判断基準
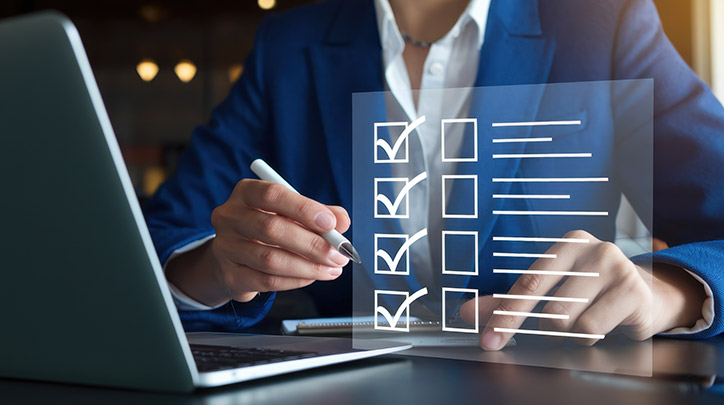
メールの保存も、不必要なメールの削除も必要ですが、保存と削除の判断基準は社内であらかじめ決めておく必要があります。個人の価値観にゆだねてしまうと、保存しなければならないメールも消してしまう可能性があるからです。
どのようにメールの保存と削除のルールを決めたらいいのか、判断基準をご紹介します。
メール保存のルール制定の第一歩は法令順守
企業におけるメール保存は、法令を遵守できるように保存することが重要です。e-文書法や税法など、メールを含む文書の保存期間に関する法令は複数存在します。
それぞれの法令によって、保存期間が異なりますが、10年間保存できる体制を整えておくと大抵の法令に対応可能です。
「どのようなメールを何年間保存しなければならないのか」、専門家の意見を聞きながら
法令を遵守できるようにルールを決めていきましょう。
メール保存が求められる例
- 電子メールで請求書や領収書(PDF等)を受領する場合
- メール本文または添付ファイルに記載された注文書・契約書・見積書などを保存する場合
電子メールで受領する請求書や領収書、また注文書や契約書などの取引情報は、法令に基づき、改ざん防止や検索性を確保した状態で、適切に保存する必要があります。
社内ポリシーの整備
法令順守を基盤にしながら、実際の業務の内容に沿った社内ポリシーを決定していきます。
どのようなメールを保存したいのかを、社内で意思統一しておくことが大切です。
また、誰が管理するのか、メールにどのように権限を設定するべきかなども明確に決めておきましょう。
メールの保存と削除のルール作りのポイント

社内ポリシーを基に、メールの保存と削除の具体的なルールを決めて、社内共有します。主に以下のことを社内に共有し、担当者全員が理解・遵守できるように周知・教育を行うことが重要です。
- どのようなメールを保存対象にするのか
- どの部署がどのメールを管理するのか
- メールの保存形式や保存場所(オンプレ・クラウドなど)
- メール削除の手順や承認フロー
- 保存期間満了後のメールの扱い
また、メールの保存・削除のルールは定期的な見直しを行い、法令の改正や社内業務の変化に対応できる柔軟な体制づくりも欠かせません。これにより、情報漏洩リスクの低減や効率的なメール管理が可能となり、企業の信頼性向上にもつながります。
ポイントは情報の重要度に応じた管理レベルの設定
すべてのメールを同じように扱うのではなく、「社内連絡」「営業資料」「契約書・顧客情報」など、機密性や重要性に応じた分類ルールを定めることで、適切な保存期間や削除のタイミングが明確になります。
メールの管理を楽にする方法

メールの保存や削除を手動で行うと、ミスや属人化が生じやすく業務効率が低下します。そこで、メール管理システムやアーカイブサービスを活用し、全メールを自動で振り分けて保存・管理しましょう。
システムによっては、保存期間に応じた自動削除ルールを設定することで、不要なメールを定期的に削除することも可能です。
まずは、現在利用中のメールシステムに振り分け機能や削除ルール設定があるか、保存期間はどの程度かを確認し、できるだけ負担の少ない運用を目指しましょう。
効率よくメールを管理するならシステムの見直しを
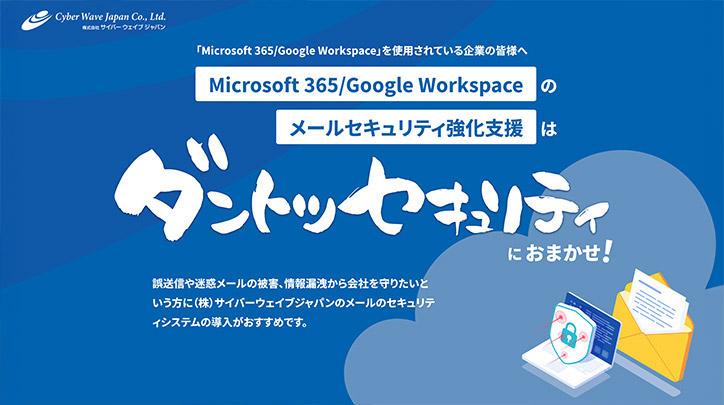
効率よく過去のメールを整理するなら、メールシステムの見直しも重要です。
株式会社サイバーウェイブジャパンでは、以下のようなメールサービスを展開しています。
- Microsoft 365やGoogle Workspaceをご利用の方に向けた「ダントツセキュリティ」
- クラウドメールをお探しの方に「CWJ Secure On(セキュアワン)」
- メールの保存や管理に便利な「MailArchive(メールアーカイブ)」
メールの運用や管理を楽にするシステムをお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。少数アカウントからのご利用や、大人数でのご利用まで、利用人数に応じて柔軟に対応可能です。
「メールの保存や管理を行いたいけど、何をしたらいいのかわからない」という方も、弊社のコンサルタントがご案内しますので気軽にご相談ください。
 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
この記事のポイント
-
1.メールを保存するメリットは?
- トラブル時の「証拠保全」や「監査対応」に活用できる
- 過去のやり取りがチーム間での情報共有や業務引き継ぎに役立つ
- 保存されたメールはナレッジとしても活用可能
メールを保存しておくと、コンプライアンス違反やトラブルが起きたときに事実確認の際に役立ちます。また、トラブル対応時のマニュアルとして活用することが可能で、業務品質の安定につながることなど、さまざまなメリットがあります。
詳しくは「メールを保存するメリット」をご覧ください。
-
2.メールを保存するか削除するかの判断基準は?
- 法令遵守(e-文書法、税法など)をベースに保存対象を決定する
- 「請求書」「契約書」などの取引文書は保存が必要
メール保存と削除のルールは社内ポリシーとして明文化し、定期的に見直すことが重要です。
詳しくは「メール保存・削除の判断基準」をご覧ください。
メールや添付ファイル経由のマルウェア対策をお探しの方は、株式会社サイバーウェイブジャパンまでお気軽にお問い合わせください。
 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら

インターネットデータセンターの運用から、クラウドサービスの提供まで行う株式会社サイバーウェイブジャパン(CWJ)のWeb担当者。
クラウドメールやデータ運用に関する弊社の知識を生かし、皆様のお役に立つ情報を発信しております。
クラウドメールの導入でお困りの方は弊社にご相談ください。
サイバーウェイブジャパンは、全国のお客様に対応しております。